医療における治療の方法は日々変化しており、以前の常識が次の時代では全く違ったアプローチになることが多々あります。
常識と根拠の狭間の難しさ
例えば、よく起こる過換気症候群の問題においては、以前は紙袋を口にあてていったん吐いた息を再度吸わせることで、血液中の炭酸ガス濃度を上昇させる方法(ペーパーバック法)がとられていましたが、この方法では血液中の酸素濃度が低くなりすぎたり、炭酸ガス濃度が過度に上昇したりする可能性があり、避けられる傾向にあります。意識的に呼吸を遅くしたり、呼吸を止めることで症状は改善するので、落ち着いた対応が必要です。
一方で、過換気は精神的に落ち着かせることが何より重要です。
紙袋を加えることによって、精神的に落ち着けば呼吸は安定する場合も多いです。根拠をどこまで現場に取り入れるかは、非常に難しい問題です。
障害予防トレーニングについても、少しずつ新しい研究が取り入れられることによって、内容が変化しています。
前十字靭帯損傷の常識を疑う
前十字靱帯損傷のリハビリテーションにおいては、膝が内側に入らないように意識させることが中心となります。これは、膝関節の外反が大きく(膝が内側に入る角度が大きい)なることによって、障害発症が増えると考えられているからです。

脳の構造から考える動き
私たちは、非常にスピーディーな展開でスポーツ動作を行う際には、意識的に行う部分と無意識に行う部分を使い分けながら動作を行っています。
例えば、空中でヘディングをするプレーを考えてみます。

ボールを目で追っている状態では、大脳皮質の視覚野というところを中心に視覚情報を得ており、ボールの落下地点を予測したり、ヘディングをどこに当ててボールを落とすかを考えます。
実際にジャンプしてヘディングをする際には、ジャンプや着地については考えることなく無意識で行うことができます。ジャンプの着地動作が無意識に行えるのは、皮質下の神経機構を中心に身体を動かすことが可能だからです。

このように、脳や神経については機能分化が行われており、同時並行で上手く活動することで高度なプレーが可能になります。
視覚情報から予測して運動を行う場合と反射的に動く場合には、筋肉を動かすための神経経路が異なります。

意識して動作を行う場合には、反射的に動かすよりも時間がかかりますが、自分のイメージした動きが作ることができます。一方で、意識して常に動かしていると無意識の時には、意識的に動かせるかどうかは分かりません。
意識して動作を行っている場合、相手がいたり、ボールを扱ったり同時並行で違う動作に意識を向けた際に無意識の動作が上手く行えないことが多々あります。
無意識な状態で適切な運動を行えるようにすることが重要です。
障害予防のパラダイムシフト
ここで、話を前十字靭帯損傷に戻します。
前十字靭帯が損傷すると、ヒトは無意識に膝を意識するようになります。
自分の身体(筋肉や靱帯にから得られる感覚)から情報を得ていたものが、視覚情報などを頼りにして、身体の位置情報を吸収する割合が高くなることが報告されています。
感覚運動制御から視覚運動制御への変換が起こるのではないかと考えられています。

また、別の研究においては、前十字靭帯損傷後に反対側の損傷が起こった患者の脳活動の研究において、視覚運動制御の活動が高くなっていたことを報告しています。
視覚運動制御が高くなったのは、前十字靭帯が切れたことによるものなのか、それとも視覚運動制御が高いから靭帯が切れたのかは明らかではありませんが、視覚に頼り過ぎた身体のコントロールは障害に関与する可能性がありそうです。

障害予防は脳から考える時代
こうした、背景から考えると障害予防に必要なことが浮かび上がってきます。
視覚的運動制御に頼ることなく、感覚運動制御を強化するように運動を組み立てていく必要があります。
ここで取るべき戦略は大きく二つです。
❶ 無意識で運動を行える能力を高める
❷ 認知処理の能力を高める

無意識での運動能力を高める
運動を自動化することができれば、障害予防に有益です。
その理由は二つあります。
一つは、運動が自動化させることによって認知処理への負担が減ります。
ドリブルがボールを見ることなく扱えるようになれば、周りの視覚情報を多く取り込むことができ、予測的な動きを早い段階で行うことが可能です。
もう一つは、正しい運動の自動化が行えれば、運動能力自体が上がるためです。例えば膝が内側に入らない状態が作れるとすれば、股関節周囲の筋力が向上したり、足関節周りの協調性が改善して、バランスが上手く取れるようになっていることが考えられます。

認知処理を高める
認知処理の速度自体を高めることができれば、高い運動能力がなくてもプレーすることは可能です。
これは、サッカーで例えるなら相手のいないスペースを素早く見つけて動いたり、相手の取れない位置にボールを置いてドリブルしたり、ボールキープをしたりすることが挙げられます。
味方と相手の状況を理解して、最適なプレーを選択する能力とも言えます。

運動能力には限界がありますが、認知処理の能力については限界はありません。
限られた自分の能力をどのように活かしていくは、認知能力の大きさが影響してくると考えられます。
パラダイムシフトが起こるか?
考えるべきことは、動き自体を意識して行うトレーニングやリハビリが本当に正しいかを考えることです。

意識すれば膝が内側に入らない状態を指導の際には、確認できたとしても、環境が変化したり、認知課題の量が多くなった際に発揮できないようであれば、トレーニングは失敗です。
頭を使いながら、思い通りのプレーができる状態を作ることが最適なトレーニングです。
Neto T, Sayer T, Theisen D, Mierau A.Functional Brain Plasticity Associated with ACL Injury: A Scoping Review of Current Evidence. Neural Plast. 2019 Dec 27;2019:3480512. doi: 10.1155/2019/3480512.
Recent Posts







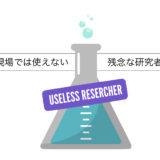
[…] 障害予防は脳から考える時代へ […]